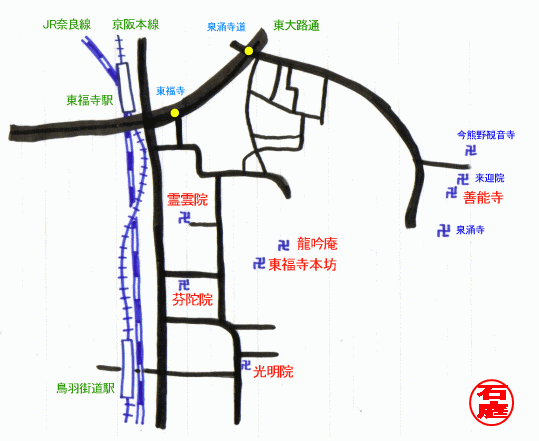■
東福寺の重森三玲探訪録
2007.9.2. ▼地上の小宇宙
2006年は東京・汐留の松下電工汐留ミュージアムで(2006年10月〜12月)、2007年は京都・松ヶ崎の京都工芸繊維大学美術工芸資料館で(2007年6月〜8月)、作庭家・重森三玲の回顧展が「重森三玲の庭−地上の小宇宙−」と題して行われた。
展覧会はこの後、静岡アートギャラリーへ巡回する(2007年10月〜11月)。
(※展覧会のレポはこちら)
東京展も京都展も、内容はさして変わらず、という感じであったので、静岡展も同様の内容になるのだろう。
実際に重森三玲の庭を見るならば、やはり京都市内が手軽だ。常時公開している寺社だけでも、僕が知っている限りでは7ヶ所。 中でも、東福寺方丈をはじめ、その周辺の塔頭寺院には、重森三玲に縁のある寺院が点在している。
8月に京都展を訪れた後、いくつかの「重森三玲の庭」をまとめて歩いてみた。こうやって、ひとつのテーマをもって散策するのも楽しいもの。
といっても、庭を見る僕の目は下手の横好き程度のものなので、素人の感想程度に読み流して、散策のちょっとしたヒントにでもなればいいなと思います。
▼光明院「波心庭」
まずは京阪本線の鳥羽街道駅を降りて東へ。光明院からスタート。
ここには「波心庭」と呼ばれる広々とした庭がある。
観光目的の寺院ではないのだが、おそらくはお寺の好意によって開放されており、我々は重森三玲の庭を見る機会に恵まれている。
拝観料は志納。玄関に立て掛けられている竹筒に志を納めて中に入る。
数年前にはJR東海のポスターに用いられたこともあったが、それでも今もなお“知る人ぞ知る”的なスポットとして、喧騒から離れた空間にある。 過去に何度も足を運んでいるが、紅葉の季節のわずかな期間を除いては、人と居合わせることがあっても数人、時には庭を独り占めしてしまう幸運に恵まれることも稀ではない。
庭園研究で出発した重森三玲は、昭和14年(1939年)に実質上のデビュー作とされる東福寺方丈庭園を手掛けたが、ここの「波心庭」も同時期のものであり、重森三玲の初期作品を代表するものとして知られている。
広々とした空間の中で、波打つような丘がなだらかな曲線を描き、所々に大中小の立石が配されている。 また、白砂を囲む曲線も柔らかく、全体的に穏やかで、ゆとりのある印象を受ける。
また、この波心庭は、書院や本堂の中から眺める上で、どこから見ても楽しめるように、緻密な計算がされているようにも思える。
まずは玄関を上がった時に目に飛び込んでくる三尊石。我々の視線を、まずは一点に引きつける。 そして、三ヶ所に配置された三尊の石組が、ともすれば締まりがなくなりがちな広い空間の中で絶妙なアクセントとなっており、建物内のどの場所からでも三尊石組の美しい立ち姿を見ることができる。
白砂は海、苔は陸地。
造園当時の写真を見ると、白砂の上に栗石を点々と置いて水の泡を表現するといった手段が取られていたが、その後、栗石は排されて、マイナーチェンジを経て現在に至っている。
▼東福寺方丈「八相の庭」
光明院を出たら、北へ向かって東福寺を目指す。
歩くこと数分。
六波羅門から境内に入って、三門と本堂の威容を左に見ながら方丈へと向かう。
東福寺の方丈庭園は、方丈の四方を囲むようにして四つの庭があり、「八相の庭」と称されている。
重森三玲が43歳の時(昭和14年)に手掛けた実質上のデビュー作であり、同時にまた、三玲の代表作であり、日本の近代庭園の代表作ともされている。 東福寺の調査を手掛けていた時に、方丈の造園計画の話を持ちかけられたことをきっかけに、ボランティアで造園を引き受けたという。
庫裡で拝観の受付を済ませ、廊下を歩いて視界が開けると、まず目に飛び込んでくるのが、方丈南庭の峻険な石群だ。 光明院の「波心庭」といい、人の視界に飛び込んでくる最初の光景にインパクトを持たせるのは、この当時の重森三玲の確信犯的な狙いだろうか。
そしてまた、こうした大きな立石を配して動きのある(動きを感じさせる)庭園を作成するというスタイルは、三玲にとって終生変わらぬものとなり、 僕のような素人の目にも「重森三玲の庭!」と印象付けるような、作庭家の個性を表すものとなった。
立石での表現は、三玲にとっては古代と現代(モダン)をリンクさせる試みだったのだろう。 江戸中期以降の庭園を芸術性の乏しいものとして考えた三玲は、石が神性を持ち信仰の対象となっていた時代、 すなわち古代の磐座(いわくら)や磐境(いわさか)といった石組に原点を見出し、 それを現代の庭園において再解釈・再構築して、現代の庭園造りにパワーを呼び戻そうとしたのではなかったか。
……と、そんな思いもほどほどに切り上げて、方丈の「八相の庭」をさらに歩く。
西庭の「井田市松」の庭は、南庭の白砂と巨石による表現から一転して、砂地とサツキの刈込みが市松模様を描き、とても色彩豊かな庭だ。 通天橋の景色を背景に借りて、秋深まった紅葉の季節の眺めがとくに素晴らしい。
方丈北庭は「市松の庭」。苔と石で市松模様を描き、こちらも幾何学的なデザインへの取り組みがうかがわれる。 市松模様を作る石は、もともと方丈南の恩賜門内にあった敷石を再利用したもの。
最後に東庭「北斗の庭」。白砂の上に円柱の石材を北斗七星の型に配置する。この庭を構成する石は、東司(便所)の柱石の余りの再利用だ。
南庭の巨石による表現と、廃材・余材の石で作った庭との対比もまた、東福寺方丈庭園の面白いところだ。 四者四様の表情を見せる庭のデザインもさることながら、北斗の庭や市松の庭に見られるように、本来は捨てられるべきであった石を再利用するなど、 素材にこだわらず(むしろ素材の不利な面を逆転の発想で生かして)、重森三玲が自由で柔軟な精神で庭造りに取り組んだことをうかがわせる。
▼龍吟庵「龍吟庭」「不離の庭」
方丈を出て、境内の奥へと進む。
通天橋・臥雲橋とともに、東福寺三名橋と呼ばれる偃月橋(えんげつきょう)を渡ると、そこは龍吟庵。
東福寺第三世住持・大明国師(1212〜1291)の住居跡で、方丈の背後の開山堂で大明国師を祀る。 龍吟庵の方丈は室町時代の建立で、方丈建築としては現存する最古の建物として国宝指定されている。 常時公開はしていないので、春秋冬のいずれかの季節に公開されることを願って足を運ぶしかない。
重森三玲は、この龍吟庭においても庭造りを手掛けた。方丈「八相の庭」から時代を下って、昭和39年・68歳の時のことだ。
いちばんの見どころは、方丈西の庭。寺名にちなんで「龍吟庭」と呼ばれる。
白砂と黒砂で雲の姿を表し、中心に置かれた3つの立石による石組によって、昇天する龍の頭と2本の角が雲の隙間から出現する場面を表現している。 そして、この立石を中心にして、周囲にめぐらされた平石を目で追っていくと、龍がとぐろを巻くように、細長いからだをうねらせているのが分かるだろう。
秋も深まると、この白と黒の世界に鮮烈な赤い色が加わる。庭の背後の木々が葉を落としはじめると、龍の頭が赤く染まる。 まるで……血しぶきでも上げながら、さらに猛々しく龍が昇天していくようにも感じられる。
龍吟庵では、さらに二つの庭を見ることができる。
南庭(前庭)は白砂を敷いただけのシンプルな庭。竹垣には稲妻模様が施されている。
東庭は「不離の庭」。鞍馬の赤石を砕いて敷いた、珍しい色合いの庭だ。
この庭は、龍吟庵の開創・大明国師の故事にちなむ。 大明国師が幼少の頃に熱病を患って山の中に捨てられた時、六匹の狼に襲われそうになった国師を二頭の犬が守った、という故事だ。
中央のやや小さい平石が国師。その両隣りが二頭の犬。手前と最奥に置かれた3つずつの石が、国師を襲おうとする狼。 国師から離れなかった二頭の犬の姿が、文字通りの不離を表す。
▼芬陀院(雪舟寺)「鶴亀の庭」の復元
東福寺の日下門を出て、そのまままっすぐ西へ向かうと、左手に東福寺塔頭の芬陀院の門が立つ。
「雪舟庭園」の札が掲げられているとおり、雪舟作と伝えられる庭園が残っており、よって雪舟寺とも呼ばれている。 とてもこじんまりとしたお寺で、訪れる拝観客もわずかだ。静かに心を落ち着けたい人には、ふさわしい場所だと思う。
3年ほど前に訪れた時は、夏の暑い日に麦茶が用意されており、自由に飲んでよかったのだが、ここ最近は見かけない(ちょっと淋しい)。
室町後期の画家・雪舟(1420〜1506)は、はじめ亀の絵を描くことを所望されたのだったが、実際に出来上がったのは、絵ではなくて鶴亀の庭だったと伝えられている。
この庭は、石が散在するなど長いこと荒廃していたが、重森三玲によって復元された。 復元するにあたり、雪舟作と伝わるいくつかの寺院の庭を参考にしたというが、庭園研究家として日本各地の庭を実測調査した経験が、こんなところにも生かされたのだろう。
庭に向かって、左が鶴島、右が亀島。白砂と苔の対比が美しく、とてもシンプルな庭だ。
亀島の亀石が、庭を作ったその夜に動いたとか、夜毎に動いていたとか、そんな「動く亀石」の言い伝えまでが残っており、 さらには、亀島に立つ石は、雪舟が亀石が動かぬように突き立てたものだという話まで伝わっている。
また、書院の東庭は、重森三玲によるもの。やはり鶴亀の庭である。
とても地味な印象を受けるが、おそらくは南庭とのバランスを考えてのことなのだろう。 雪舟の庭と同様に鶴亀をモチーフに用いたことは、あるいは、雪舟に対するリスペクトの意味も含まれていたのかもしれない。
▼霊雲院「九山八海の庭」「臥雲の庭」
東福寺の日下門まで戻り、北へと歩を進める。
東福寺三名橋のひとつ、臥雲橋を渡る。
橋の上では、上流の通天橋に向かってカメラを向ける人の姿をしばしば見掛ける。 また、この橋は日常生活の通路にもなっているので、近隣の住民が散歩をする姿も見掛けられる。
臥雲橋を渡ると左手に入っていく路地があり、路地の突き当たりが霊雲院だ。拝観客の姿が少なく、閑散とした場所である。
ここでもまた、重森三玲の二つの仕事を見ることができる。
まずは九山八海の庭。
荒れ果てていた庭を重森三玲が昭和45年(1970年)頃に復元した。
庭の中央には「遺愛石」と呼ばれる石が置かれている。 霊雲院の和尚・湘雪と親交を持っていた肥後藩主・細川光尚(1619-1650)が、須弥台と石船を作って「遺愛石」と名付け、自身が帰依していた湘雪に贈ったものだ。
この遺愛石は須弥山を表しており、重森三玲はこの石を中心にして、須弥山を中心とした九つの山と八つ海を表す仏教世界(九山八海)を庭園として再構築した。
また、書院の西側には、やはり重森三玲が手掛けた臥雲の庭がある(昭46年・1971年頃か)。
白砂と赤砂のコントラストが鮮やかだ。白砂は渓谷を流れる水か。赤砂は雲か霧か。赤く染まっているのは、朝焼けか夕焼けの時間帯を表しているのかもしれない。 また、庭の最奥に組まれた、寄り添うような三つの立石が目を惹く。
こちらの庭は、視点が落ち着かないというか、ごちゃごちゃとしている感じが否めない。
▼さらに泉涌寺の方へ足を伸ばすと…
東福寺エリアをまわってもまだ時間が余っていたら、泉涌寺の方面へ足を伸ばしてみる。歩いて20分程度だろうか。
泉涌寺方面への道は、東福寺の裏手の細い路地をごちゃごちゃと歩いていくのが近道なのだが、 方角に自信がない人は、多少遠回りになるが、東大路通の泉涌寺道入り口まで戻って、坂を上っていくという方法が良い(このルートも、しだいに森深くなっていく様子が楽しい)。
途中、泉涌寺道から脇道に入ると、泉涌寺塔頭の来迎院の向かいに善能寺という無人のお寺がある。 観光ガイドには載らない、まさに"知る人ぞ知る"という場所だ。
僕がここに立ち寄ったのも、本当に偶然のことだった。 数年前に「目に入るお寺の門をかたっぱしからくぐっていく」という方法で泉涌寺エリアを散策したとき、 来迎院の次に立ち寄ったのが、この善能寺だった。
門をくぐると、ぽっかりと口をあけた空間に、お堂がひとつ建っている。
本堂自体は新しい建物だ。航空機の事故で亡くなった方の遺族が、航空機事故の殉難者の霊を弔い、事故の絶無を祈願するために寄進した。 昭和46年(1971年)の建立。
この本堂のとなりにひっそりとあるのが、重森三玲の手による庭園「遊仙苑」(昭和47年・1972年)だ。
これまで見てきた三玲の庭はいずれも枯山水庭園だったが、こちらは峻険な立石が池を取り囲む池泉式の庭園となっている(しかし、きちんと水が入っていない)。
周囲の草が伸びており、捨て置かれてしまったかのような佇まいが何とも淋しいかぎりだが、それゆえにというか、庭を見るための拝観料などは必要ないし、 さらには、庭の中に足を踏み入れて、重森三玲の石組を間近に見て、手に触れることさえできてしまう。
▼永遠のモダン
重森三玲が好んで使った言葉に、「永遠のモダン」というものがある。
重森展では、重森三玲の庭造りの様子を撮影したビデオ上映が行われており、このビデオの中では重森自身が「永遠のモダン」について語るシーンが盛り込まれていた。
日本庭園とは自然を模倣してきれいに作ったものが良いというわけではない、たとえば龍安寺の石庭に代表されるように、優れた庭園ほど抽象的な志向を持っており、 そうした庭園こそがいつの時代にも「モダン」なものとして受け入れられる、いわば、そうした「永遠のモダン」を追求した庭造りをしたい……と、たしか、そのような内容だったと思う (耳で聞いて覚えただけなので、違っているかもしれません)。
「永遠のモダン」は、今では重森三玲を語る上で欠かせないキーワードになっている。
しかし、重森三玲の庭の「永遠のモダン」への挑戦は、まだ始まったばかりではないかと思う。 三玲の庭が「永遠」を訴える力を備えるのかどうかは、今後50年、あるいは100年……という時間の流れと価値観の変遷との未知なる戦いでもある。
没後22年。近年、再評価の機運が芽生えつつあるが、重森三玲の手掛けた庭には、荒れ放題になっているものも多いと聞く。 最近ではボランティアで三玲の庭を整備したいという人たちが現れているとも聞く。 けれども、整備をしたらしたで、今度は管理する側にも維持をするための費用がかかるだろう。
三玲の庭を後世に残すためには、まずは三玲の庭を広く一般に公開できるような環境づくり、それが必要になるのかもしれない。
【重森三玲を歩く東福寺周辺マップ】
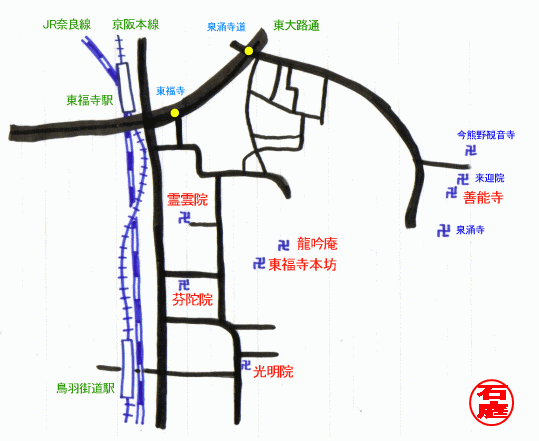
2007.9.2. ▼地上の小宇宙

|

|
| 東京展ポスター | 京都展ポスター |
(※展覧会のレポはこちら)
東京展も京都展も、内容はさして変わらず、という感じであったので、静岡展も同様の内容になるのだろう。
実際に重森三玲の庭を見るならば、やはり京都市内が手軽だ。常時公開している寺社だけでも、僕が知っている限りでは7ヶ所。 中でも、東福寺方丈をはじめ、その周辺の塔頭寺院には、重森三玲に縁のある寺院が点在している。
8月に京都展を訪れた後、いくつかの「重森三玲の庭」をまとめて歩いてみた。こうやって、ひとつのテーマをもって散策するのも楽しいもの。
といっても、庭を見る僕の目は下手の横好き程度のものなので、素人の感想程度に読み流して、散策のちょっとしたヒントにでもなればいいなと思います。
▼光明院「波心庭」

|
| この栗石は造園当時のものの名残か? |
ここには「波心庭」と呼ばれる広々とした庭がある。
観光目的の寺院ではないのだが、おそらくはお寺の好意によって開放されており、我々は重森三玲の庭を見る機会に恵まれている。
拝観料は志納。玄関に立て掛けられている竹筒に志を納めて中に入る。
数年前にはJR東海のポスターに用いられたこともあったが、それでも今もなお“知る人ぞ知る”的なスポットとして、喧騒から離れた空間にある。 過去に何度も足を運んでいるが、紅葉の季節のわずかな期間を除いては、人と居合わせることがあっても数人、時には庭を独り占めしてしまう幸運に恵まれることも稀ではない。
庭園研究で出発した重森三玲は、昭和14年(1939年)に実質上のデビュー作とされる東福寺方丈庭園を手掛けたが、ここの「波心庭」も同時期のものであり、重森三玲の初期作品を代表するものとして知られている。
広々とした空間の中で、波打つような丘がなだらかな曲線を描き、所々に大中小の立石が配されている。 また、白砂を囲む曲線も柔らかく、全体的に穏やかで、ゆとりのある印象を受ける。
また、この波心庭は、書院や本堂の中から眺める上で、どこから見ても楽しめるように、緻密な計算がされているようにも思える。
まずは玄関を上がった時に目に飛び込んでくる三尊石。我々の視線を、まずは一点に引きつける。 そして、三ヶ所に配置された三尊の石組が、ともすれば締まりがなくなりがちな広い空間の中で絶妙なアクセントとなっており、建物内のどの場所からでも三尊石組の美しい立ち姿を見ることができる。
白砂は海、苔は陸地。
造園当時の写真を見ると、白砂の上に栗石を点々と置いて水の泡を表現するといった手段が取られていたが、その後、栗石は排されて、マイナーチェンジを経て現在に至っている。

|

|
| 座る場所をあちこち変えながら楽しみたい「波心庭」 |
▼東福寺方丈「八相の庭」

|
| 峻険な石組を配した方丈南庭 |
歩くこと数分。
六波羅門から境内に入って、三門と本堂の威容を左に見ながら方丈へと向かう。
東福寺の方丈庭園は、方丈の四方を囲むようにして四つの庭があり、「八相の庭」と称されている。
重森三玲が43歳の時(昭和14年)に手掛けた実質上のデビュー作であり、同時にまた、三玲の代表作であり、日本の近代庭園の代表作ともされている。 東福寺の調査を手掛けていた時に、方丈の造園計画の話を持ちかけられたことをきっかけに、ボランティアで造園を引き受けたという。
庫裡で拝観の受付を済ませ、廊下を歩いて視界が開けると、まず目に飛び込んでくるのが、方丈南庭の峻険な石群だ。 光明院の「波心庭」といい、人の視界に飛び込んでくる最初の光景にインパクトを持たせるのは、この当時の重森三玲の確信犯的な狙いだろうか。
そしてまた、こうした大きな立石を配して動きのある(動きを感じさせる)庭園を作成するというスタイルは、三玲にとって終生変わらぬものとなり、 僕のような素人の目にも「重森三玲の庭!」と印象付けるような、作庭家の個性を表すものとなった。
立石での表現は、三玲にとっては古代と現代(モダン)をリンクさせる試みだったのだろう。 江戸中期以降の庭園を芸術性の乏しいものとして考えた三玲は、石が神性を持ち信仰の対象となっていた時代、 すなわち古代の磐座(いわくら)や磐境(いわさか)といった石組に原点を見出し、 それを現代の庭園において再解釈・再構築して、現代の庭園造りにパワーを呼び戻そうとしたのではなかったか。
……と、そんな思いもほどほどに切り上げて、方丈の「八相の庭」をさらに歩く。
西庭の「井田市松」の庭は、南庭の白砂と巨石による表現から一転して、砂地とサツキの刈込みが市松模様を描き、とても色彩豊かな庭だ。 通天橋の景色を背景に借りて、秋深まった紅葉の季節の眺めがとくに素晴らしい。
方丈北庭は「市松の庭」。苔と石で市松模様を描き、こちらも幾何学的なデザインへの取り組みがうかがわれる。 市松模様を作る石は、もともと方丈南の恩賜門内にあった敷石を再利用したもの。
最後に東庭「北斗の庭」。白砂の上に円柱の石材を北斗七星の型に配置する。この庭を構成する石は、東司(便所)の柱石の余りの再利用だ。
南庭の巨石による表現と、廃材・余材の石で作った庭との対比もまた、東福寺方丈庭園の面白いところだ。 四者四様の表情を見せる庭のデザインもさることながら、北斗の庭や市松の庭に見られるように、本来は捨てられるべきであった石を再利用するなど、 素材にこだわらず(むしろ素材の不利な面を逆転の発想で生かして)、重森三玲が自由で柔軟な精神で庭造りに取り組んだことをうかがわせる。

|

|

|
| 西庭:井田市松 | 北庭:市松 | 東庭:北斗 |
▼龍吟庵「龍吟庭」「不離の庭」

|
| 秋になると白と黒の世界に赤が加わる「龍吟庭」 |
通天橋・臥雲橋とともに、東福寺三名橋と呼ばれる偃月橋(えんげつきょう)を渡ると、そこは龍吟庵。
東福寺第三世住持・大明国師(1212〜1291)の住居跡で、方丈の背後の開山堂で大明国師を祀る。 龍吟庵の方丈は室町時代の建立で、方丈建築としては現存する最古の建物として国宝指定されている。 常時公開はしていないので、春秋冬のいずれかの季節に公開されることを願って足を運ぶしかない。
重森三玲は、この龍吟庭においても庭造りを手掛けた。方丈「八相の庭」から時代を下って、昭和39年・68歳の時のことだ。
いちばんの見どころは、方丈西の庭。寺名にちなんで「龍吟庭」と呼ばれる。
白砂と黒砂で雲の姿を表し、中心に置かれた3つの立石による石組によって、昇天する龍の頭と2本の角が雲の隙間から出現する場面を表現している。 そして、この立石を中心にして、周囲にめぐらされた平石を目で追っていくと、龍がとぐろを巻くように、細長いからだをうねらせているのが分かるだろう。
秋も深まると、この白と黒の世界に鮮烈な赤い色が加わる。庭の背後の木々が葉を落としはじめると、龍の頭が赤く染まる。 まるで……血しぶきでも上げながら、さらに猛々しく龍が昇天していくようにも感じられる。
龍吟庵では、さらに二つの庭を見ることができる。
南庭(前庭)は白砂を敷いただけのシンプルな庭。竹垣には稲妻模様が施されている。
東庭は「不離の庭」。鞍馬の赤石を砕いて敷いた、珍しい色合いの庭だ。
この庭は、龍吟庵の開創・大明国師の故事にちなむ。 大明国師が幼少の頃に熱病を患って山の中に捨てられた時、六匹の狼に襲われそうになった国師を二頭の犬が守った、という故事だ。
中央のやや小さい平石が国師。その両隣りが二頭の犬。手前と最奥に置かれた3つずつの石が、国師を襲おうとする狼。 国師から離れなかった二頭の犬の姿が、文字通りの不離を表す。

|

|
| 白砂を敷いただけの南庭。竹垣は稲妻をかたどる。 | 東庭「不離の庭」。こちらも竹垣のデザインが面白い。 |
▼芬陀院(雪舟寺)「鶴亀の庭」の復元

|
| 図南亭から眺める東庭 |
「雪舟庭園」の札が掲げられているとおり、雪舟作と伝えられる庭園が残っており、よって雪舟寺とも呼ばれている。 とてもこじんまりとしたお寺で、訪れる拝観客もわずかだ。静かに心を落ち着けたい人には、ふさわしい場所だと思う。
3年ほど前に訪れた時は、夏の暑い日に麦茶が用意されており、自由に飲んでよかったのだが、ここ最近は見かけない(ちょっと淋しい)。
室町後期の画家・雪舟(1420〜1506)は、はじめ亀の絵を描くことを所望されたのだったが、実際に出来上がったのは、絵ではなくて鶴亀の庭だったと伝えられている。
この庭は、石が散在するなど長いこと荒廃していたが、重森三玲によって復元された。 復元するにあたり、雪舟作と伝わるいくつかの寺院の庭を参考にしたというが、庭園研究家として日本各地の庭を実測調査した経験が、こんなところにも生かされたのだろう。
庭に向かって、左が鶴島、右が亀島。白砂と苔の対比が美しく、とてもシンプルな庭だ。
亀島の亀石が、庭を作ったその夜に動いたとか、夜毎に動いていたとか、そんな「動く亀石」の言い伝えまでが残っており、 さらには、亀島に立つ石は、雪舟が亀石が動かぬように突き立てたものだという話まで伝わっている。
また、書院の東庭は、重森三玲によるもの。やはり鶴亀の庭である。
とても地味な印象を受けるが、おそらくは南庭とのバランスを考えてのことなのだろう。 雪舟の庭と同様に鶴亀をモチーフに用いたことは、あるいは、雪舟に対するリスペクトの意味も含まれていたのかもしれない。

|
| 南庭は雪舟作の鶴亀の庭を重森三玲が復元 |
▼霊雲院「九山八海の庭」「臥雲の庭」

|
| 臥雲の庭 |
東福寺三名橋のひとつ、臥雲橋を渡る。
橋の上では、上流の通天橋に向かってカメラを向ける人の姿をしばしば見掛ける。 また、この橋は日常生活の通路にもなっているので、近隣の住民が散歩をする姿も見掛けられる。
臥雲橋を渡ると左手に入っていく路地があり、路地の突き当たりが霊雲院だ。拝観客の姿が少なく、閑散とした場所である。
ここでもまた、重森三玲の二つの仕事を見ることができる。
まずは九山八海の庭。
荒れ果てていた庭を重森三玲が昭和45年(1970年)頃に復元した。
庭の中央には「遺愛石」と呼ばれる石が置かれている。 霊雲院の和尚・湘雪と親交を持っていた肥後藩主・細川光尚(1619-1650)が、須弥台と石船を作って「遺愛石」と名付け、自身が帰依していた湘雪に贈ったものだ。
この遺愛石は須弥山を表しており、重森三玲はこの石を中心にして、須弥山を中心とした九つの山と八つ海を表す仏教世界(九山八海)を庭園として再構築した。
また、書院の西側には、やはり重森三玲が手掛けた臥雲の庭がある(昭46年・1971年頃か)。
白砂と赤砂のコントラストが鮮やかだ。白砂は渓谷を流れる水か。赤砂は雲か霧か。赤く染まっているのは、朝焼けか夕焼けの時間帯を表しているのかもしれない。 また、庭の最奥に組まれた、寄り添うような三つの立石が目を惹く。
こちらの庭は、視点が落ち着かないというか、ごちゃごちゃとしている感じが否めない。

|
| 九山八海の庭。中央の石が遺愛石。 |
▼さらに泉涌寺の方へ足を伸ばすと…

|
| 善能寺「遊仙苑」は忘れられたかのようにひっそりと… |
泉涌寺方面への道は、東福寺の裏手の細い路地をごちゃごちゃと歩いていくのが近道なのだが、 方角に自信がない人は、多少遠回りになるが、東大路通の泉涌寺道入り口まで戻って、坂を上っていくという方法が良い(このルートも、しだいに森深くなっていく様子が楽しい)。
途中、泉涌寺道から脇道に入ると、泉涌寺塔頭の来迎院の向かいに善能寺という無人のお寺がある。 観光ガイドには載らない、まさに"知る人ぞ知る"という場所だ。
僕がここに立ち寄ったのも、本当に偶然のことだった。 数年前に「目に入るお寺の門をかたっぱしからくぐっていく」という方法で泉涌寺エリアを散策したとき、 来迎院の次に立ち寄ったのが、この善能寺だった。
門をくぐると、ぽっかりと口をあけた空間に、お堂がひとつ建っている。
本堂自体は新しい建物だ。航空機の事故で亡くなった方の遺族が、航空機事故の殉難者の霊を弔い、事故の絶無を祈願するために寄進した。 昭和46年(1971年)の建立。
この本堂のとなりにひっそりとあるのが、重森三玲の手による庭園「遊仙苑」(昭和47年・1972年)だ。
これまで見てきた三玲の庭はいずれも枯山水庭園だったが、こちらは峻険な立石が池を取り囲む池泉式の庭園となっている(しかし、きちんと水が入っていない)。
周囲の草が伸びており、捨て置かれてしまったかのような佇まいが何とも淋しいかぎりだが、それゆえにというか、庭を見るための拝観料などは必要ないし、 さらには、庭の中に足を踏み入れて、重森三玲の石組を間近に見て、手に触れることさえできてしまう。

|
| 無人の本堂だけがぽっかりと口をあけた空間に建つ。 |
▼永遠のモダン
重森三玲が好んで使った言葉に、「永遠のモダン」というものがある。
重森展では、重森三玲の庭造りの様子を撮影したビデオ上映が行われており、このビデオの中では重森自身が「永遠のモダン」について語るシーンが盛り込まれていた。
日本庭園とは自然を模倣してきれいに作ったものが良いというわけではない、たとえば龍安寺の石庭に代表されるように、優れた庭園ほど抽象的な志向を持っており、 そうした庭園こそがいつの時代にも「モダン」なものとして受け入れられる、いわば、そうした「永遠のモダン」を追求した庭造りをしたい……と、たしか、そのような内容だったと思う (耳で聞いて覚えただけなので、違っているかもしれません)。
「永遠のモダン」は、今では重森三玲を語る上で欠かせないキーワードになっている。
しかし、重森三玲の庭の「永遠のモダン」への挑戦は、まだ始まったばかりではないかと思う。 三玲の庭が「永遠」を訴える力を備えるのかどうかは、今後50年、あるいは100年……という時間の流れと価値観の変遷との未知なる戦いでもある。
没後22年。近年、再評価の機運が芽生えつつあるが、重森三玲の手掛けた庭には、荒れ放題になっているものも多いと聞く。 最近ではボランティアで三玲の庭を整備したいという人たちが現れているとも聞く。 けれども、整備をしたらしたで、今度は管理する側にも維持をするための費用がかかるだろう。
三玲の庭を後世に残すためには、まずは三玲の庭を広く一般に公開できるような環境づくり、それが必要になるのかもしれない。
【重森三玲を歩く東福寺周辺マップ】