■
南禅寺の虎
2007.7.15.
南禅寺の庫裏で拝観料を払い、広々とした廊下を歩いていくと左手に視界がひらける。
ちょっと胸躍る瞬間だ。
目に飛び込んでくる建物は国宝の方丈、その南側には「虎の子渡しの庭」と呼ばれる枯山水庭園。こちらは小堀遠州による作庭と伝わる。
方丈の広縁を進み、右に折れると「如心庭」と名付けられた西庭。
さらに進むと、方丈の後方に続く小方丈(これも国宝建築)に足を踏み入れることとなる。
ここにやって来ると、僕が時間を掛けて立ち止まる場所がある。
小方丈、虎の間。
この部屋では狩野探幽の手によると伝わる「群虎図」の障壁画を見ることができる。
いちばん奥の部屋の正面には「水呑みの虎」として知られる、もっとも有名な図。 左に目を向けると、虎と豹の図。
なぜ虎と豹が一緒に……というのも、当時は豹が虎の雌と考えられていたので、江戸時代の画にはしばしばこういったものが存在する。
小方丈の廊下は、障子紙で自然光が濾過されて仄暗く、さらに部屋の奥にある金襖を見るには、光は頼りなく、弱々しい。
部屋に上がることを許されていない我々は、廊下から襖絵を眺めるしかないのだが、探幽の「水呑みの虎」はいっそう濃い闇に包まれており、おぼろげな姿を見せている。
虎と対峙するように部屋の前に佇み、薄闇に目を凝らす。
ここで金色の襖絵を眺める時は、晴れた日がいい。
ただし、雲ひとつないような青空ではないほうがいい。
適度に雲があって、青い空と白い雲のコントラストにメリハリのある空模様が好ましい。
そして、次から次へと雲が風に流れされて、時々、太陽を覆い隠し、また力強く日が射してくるような、光の表情に変化の富む天候が良い。
背後の障子紙越しの目まぐるしい光の強弱が、金襖に視覚的な効果を与えてくれるのだ。
太陽が雲に隠れた時は光が弱まり、襖に描かれた虎は薄闇の中に沈殿していく。
そして、太陽がふたたび姿を現したとき、闇の中からすーっと虎の姿が立ち現れ、襖の金箔は障子越しのおぼろげな光をここぞとばかりに吸い取って、輝きはじめる。
その様子は感動的ですらあり、初めてその光景に出くわした時は、鳥肌が立つくらいに心を揺り動かされた。
以来、この南禅寺の探幽の「水呑みの虎」には思い入れがあって、ただ見ることができればいいというのではなくて、南禅寺の方丈に足を運ぶ場合には、その日の空と雲の様子なども考えに入れたりしている。
僕なりの、数少ない、ささやかな、京都散策のこだわりともいえる。
この「虎の間」の前で金箔の襖絵群を眺めていると、いつも思い出すのが谷崎潤一郎のエッセイ「陰翳礼賛」だ。
僕が高校生の頃に、現代文の教科書の中でこのエッセイを初めて読んだのだったが(定番)、そこに抜粋して掲載されていたのは、わずかに漆器に関するくだりだったと記憶している。
後日、中公文庫で購入して全文を読み直してみたけれども、当時の僕には著者の言わんとする「美」がどういうことなのだか実感が持てず、ほとんど分からなかった。 でも、わざわざ本を買って、分からないなりにも読んだのだから、きっと何かしら僕の心にふれるものがあったのだろう。
その「陰翳礼賛」の中で、谷崎は伽藍建築の座敷と障子紙と闇との関連性にふれて、
私はその夢のような明るさをいぶかりながら眼をしばだゝく。何か眼の前にもやもやとかげろうものがあって、視力を鈍らせているように感ずる。それはそのほのじろい紙の反射が、床の間の濃い闇を追い払うには力が足らず、却って闇に弾ね返されながら、明暗の区別のつかぬ昏迷の世界を現じつゝあるからである。
と述べ、さらに金襖については、
諸君はまたそう云う大きな建物の、奥の奥の部屋へ行くと、もう全く外の光りが届かなくなった暗がりの中にある金襖や金屏風が、幾間を隔てた遠い遠い庭の明りの穂先を捉えて、ぽうっと夢のように照り返しているのを見たことはないか。その照り返しは、夕暮れの地平線のように、あたりの闇へ実に弱々しい金色の明りを投げているのであるが、私は黄金と云うものがあれほど沈痛な美しさを見せる時はないと思う。
と語る。
「昏迷の世界」「沈痛な美しさ」とは、著者自身の美意識に裏打ちされた独特の喩えで、僕が「虎の間」の前で感じた美しさも似たようなものだと、おこがましいことを言うつもりは、もちろんない。
けれども、たぶん、南禅寺の「水呑みの虎」の前での感動が、僕が何度も京都に足を運ぶことになる原点になっているのだと思う。 その感動を言葉で表すのに、谷崎のような、うまい喩えは見つからないけれども。
光と陰。陽と闇。
元来、日本の美において、この両者の境界はとても曖昧なものだったはずだ。 いや、境界すらなくて、両者は表と裏、光が陰を、陰が光を補完しあうことによって、ひとつの「美」を成立させることができたのだろう。
そして、光と陰が境界を失い、その両者のあいだで揺り動かされることによって、時間の感覚さえも失っていくのだ。あたかも昼と夜を失うかのように。
……或はまた、その部屋にいると時間の経過が分らなくなってしまい、知らぬ間に年月が流れて、出て来た時は白髪の老人になりはせぬかと云うような、「悠久」に対する一種の怖れを抱いたことはないであろうか……
2007.7.15.
I

|
| 南禅寺・方丈。南庭は「虎の子渡しの庭」。 |
ちょっと胸躍る瞬間だ。
目に飛び込んでくる建物は国宝の方丈、その南側には「虎の子渡しの庭」と呼ばれる枯山水庭園。こちらは小堀遠州による作庭と伝わる。
方丈の広縁を進み、右に折れると「如心庭」と名付けられた西庭。
さらに進むと、方丈の後方に続く小方丈(これも国宝建築)に足を踏み入れることとなる。
ここにやって来ると、僕が時間を掛けて立ち止まる場所がある。
小方丈、虎の間。
この部屋では狩野探幽の手によると伝わる「群虎図」の障壁画を見ることができる。
いちばん奥の部屋の正面には「水呑みの虎」として知られる、もっとも有名な図。 左に目を向けると、虎と豹の図。
なぜ虎と豹が一緒に……というのも、当時は豹が虎の雌と考えられていたので、江戸時代の画にはしばしばこういったものが存在する。
|
南禅寺・小方丈の廊下。水呑みの虎はいちばん奥にある。 障子戸越しの薄明かりが襖絵に効果的な光をもたらす… |

|
部屋に上がることを許されていない我々は、廊下から襖絵を眺めるしかないのだが、探幽の「水呑みの虎」はいっそう濃い闇に包まれており、おぼろげな姿を見せている。
虎と対峙するように部屋の前に佇み、薄闇に目を凝らす。
ここで金色の襖絵を眺める時は、晴れた日がいい。
ただし、雲ひとつないような青空ではないほうがいい。
適度に雲があって、青い空と白い雲のコントラストにメリハリのある空模様が好ましい。
そして、次から次へと雲が風に流れされて、時々、太陽を覆い隠し、また力強く日が射してくるような、光の表情に変化の富む天候が良い。
背後の障子紙越しの目まぐるしい光の強弱が、金襖に視覚的な効果を与えてくれるのだ。
太陽が雲に隠れた時は光が弱まり、襖に描かれた虎は薄闇の中に沈殿していく。
そして、太陽がふたたび姿を現したとき、闇の中からすーっと虎の姿が立ち現れ、襖の金箔は障子越しのおぼろげな光をここぞとばかりに吸い取って、輝きはじめる。
その様子は感動的ですらあり、初めてその光景に出くわした時は、鳥肌が立つくらいに心を揺り動かされた。
以来、この南禅寺の探幽の「水呑みの虎」には思い入れがあって、ただ見ることができればいいというのではなくて、南禅寺の方丈に足を運ぶ場合には、その日の空と雲の様子なども考えに入れたりしている。
僕なりの、数少ない、ささやかな、京都散策のこだわりともいえる。
II
この「虎の間」の前で金箔の襖絵群を眺めていると、いつも思い出すのが谷崎潤一郎のエッセイ「陰翳礼賛」だ。
僕が高校生の頃に、現代文の教科書の中でこのエッセイを初めて読んだのだったが(定番)、そこに抜粋して掲載されていたのは、わずかに漆器に関するくだりだったと記憶している。
後日、中公文庫で購入して全文を読み直してみたけれども、当時の僕には著者の言わんとする「美」がどういうことなのだか実感が持てず、ほとんど分からなかった。 でも、わざわざ本を買って、分からないなりにも読んだのだから、きっと何かしら僕の心にふれるものがあったのだろう。
|
谷崎潤一郎「陰翳礼賛」 今も読まれる教科書の定番 |
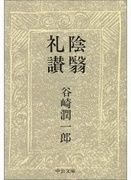
|
私はその夢のような明るさをいぶかりながら眼をしばだゝく。何か眼の前にもやもやとかげろうものがあって、視力を鈍らせているように感ずる。それはそのほのじろい紙の反射が、床の間の濃い闇を追い払うには力が足らず、却って闇に弾ね返されながら、明暗の区別のつかぬ昏迷の世界を現じつゝあるからである。
と述べ、さらに金襖については、
諸君はまたそう云う大きな建物の、奥の奥の部屋へ行くと、もう全く外の光りが届かなくなった暗がりの中にある金襖や金屏風が、幾間を隔てた遠い遠い庭の明りの穂先を捉えて、ぽうっと夢のように照り返しているのを見たことはないか。その照り返しは、夕暮れの地平線のように、あたりの闇へ実に弱々しい金色の明りを投げているのであるが、私は黄金と云うものがあれほど沈痛な美しさを見せる時はないと思う。
と語る。
「昏迷の世界」「沈痛な美しさ」とは、著者自身の美意識に裏打ちされた独特の喩えで、僕が「虎の間」の前で感じた美しさも似たようなものだと、おこがましいことを言うつもりは、もちろんない。
けれども、たぶん、南禅寺の「水呑みの虎」の前での感動が、僕が何度も京都に足を運ぶことになる原点になっているのだと思う。 その感動を言葉で表すのに、谷崎のような、うまい喩えは見つからないけれども。
光と陰。陽と闇。
元来、日本の美において、この両者の境界はとても曖昧なものだったはずだ。 いや、境界すらなくて、両者は表と裏、光が陰を、陰が光を補完しあうことによって、ひとつの「美」を成立させることができたのだろう。
そして、光と陰が境界を失い、その両者のあいだで揺り動かされることによって、時間の感覚さえも失っていくのだ。あたかも昼と夜を失うかのように。
……或はまた、その部屋にいると時間の経過が分らなくなってしまい、知らぬ間に年月が流れて、出て来た時は白髪の老人になりはせぬかと云うような、「悠久」に対する一種の怖れを抱いたことはないであろうか……
| 南禅寺・方丈と小方丈の平面図 |
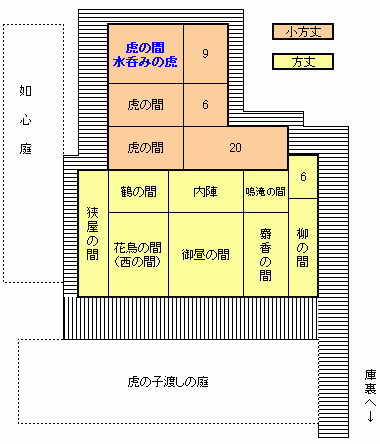
|